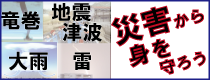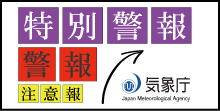大雨・台風への心得
(1)気象情報に注意し、災害の前兆現象を見逃さない。
(2)停電に備え、懐中電灯やラジオを準備する。
(3)貴重品など非常持出品を準備する。
(4)食料・飲料水を数日分確保する。
(5)浸水の恐れがあるところは生活用品を高い場所へ移す。
(6)屋根や外壁に、もろい所がないかチェックする。
(7)強風による飛来物に備えて、窓ガラスを雨戸や板で保護する。
(8)台風・大雨時には、野外活動は危険なため行わない。
備蓄品の準備
非常備蓄品(例) ※水・食料は1週間分の備蓄を!
・食料(レトルト食品、アルファ米、缶詰、菓子類、梅干、調味料など)
・水
・燃料(卓上コンロや固形燃料など)・衣類(下着、上着、タオルなど)
非常持出品(例)
・衣類(下着、上着、タオルなど)
・毛布(寝具やサバイバルシートなど)
・応急医薬品(絆創膏、傷薬、包帯、持病薬など)
・非常食品(乾パン、缶詰、ミネラルウォーター、水筒など)
・懐中電灯
・歯ブラシ、体温計、マスク
・携帯電話(充電器)
・貴重品(現金、預貯金通帳、運転免許証、健康保険証など)
防災啓発コンテンツのご紹介
・「災害から身を守ろう」(気象庁)
・「特別警報について」(気象庁)
簡単にできる水防工法のご紹介
ご家庭にあるものを使って簡単にできる水防工法をご紹介します。
ただし、これらの簡易水防工法は、あくまで小規模な水害で水深の浅い初期段階で行うものであり、避難の時期を失わないことが大切です。
1.“ごみ袋”による簡易水のう工法
家庭用ごみ袋に水を入れ、土のうの代用として使用します。
持ち運びの容易さから、40リットル程度の容量のごみ袋を二重にして中に半分程度の水を入れます。ごみ袋の強度が不足する場合には、重ねる枚数を増やします。これを出入口などに隙間なく並べます。この場合、二段重ねはできないので、10cm程度の水深が限界です。
買い物ポリ袋でも代用できます。
![]()
※簡易水のうと段ボール箱の併用
簡易水のうを段ボール箱に入れて連結させれば、水のうだけの場合に比べて強度が増し、水のうを積み重ねることもできます。
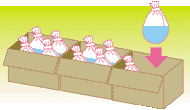
2.“ポリタンク”と“レジャーシート”による工法
10リットルまたは20リットルのポリタンクに水を入れ、レジャーシートで巻き込み、連結して使用します。
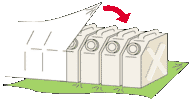
3.“プランター”と“レジャーシート”による工法
土を入れたプランターをレジャーシートで巻き込み、連結して使用します。
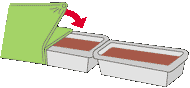
4.“止水板”による工法
長めの板などを使用し出入口の浸水を防ぎます。
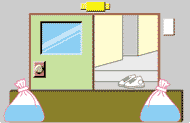
5.“吸水性ゲル水のう”による工法
土のうの代用として使用できる市販の吸水性ゲル水のうで浸水を防ぎます。
吸水性ゲル水のうは、吸水前は軽量・コンパクトですが、水を吸うと膨張する性質があります。
事務用ロッカー、テーブル、畳などを敷いて水の流入を防ぐこともできます。
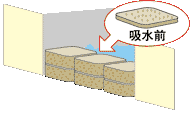
※簡単にできる水防工法のご紹介では、福岡市のイラストを使わせていただいております。